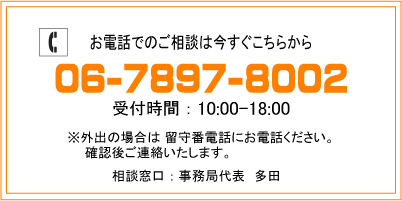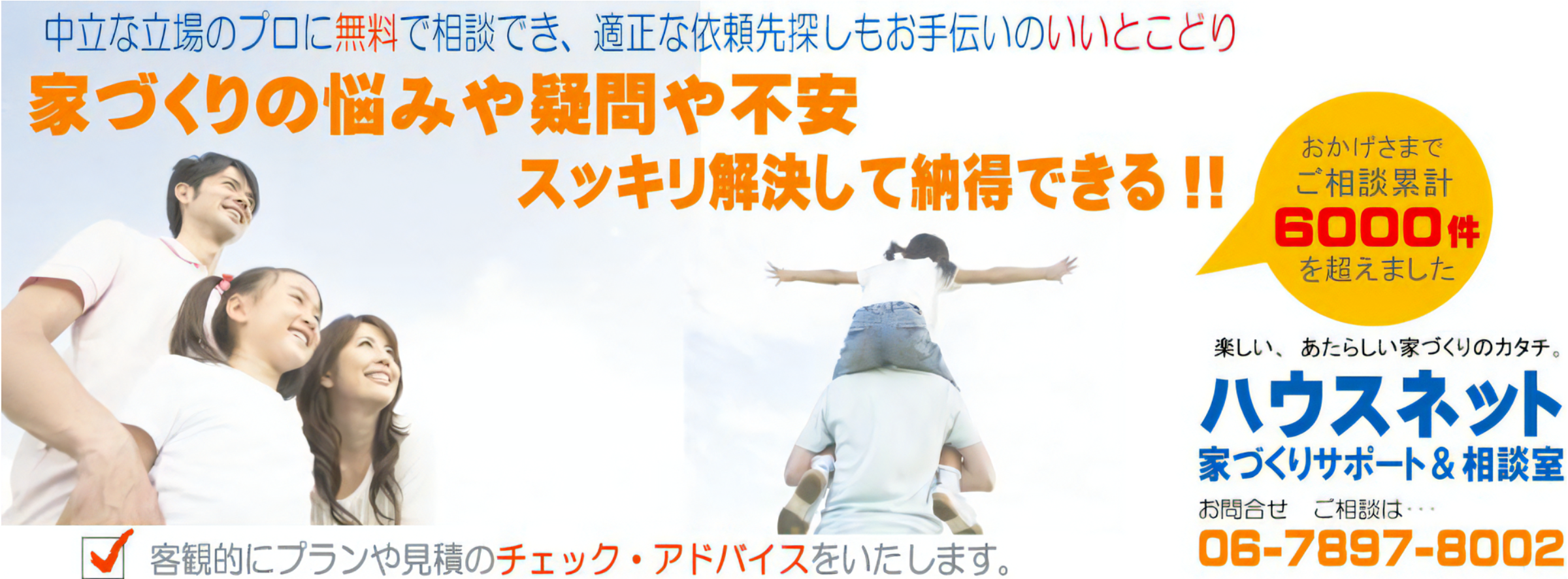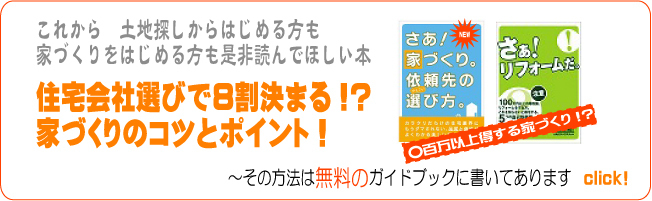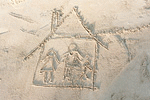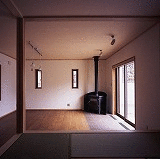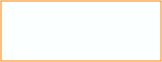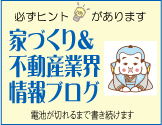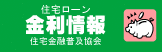原価も利益率も違うからわからない
このページでは、建築工事価格についての説明をします。
日用品など何でもそうですが、売価があって仕入れ価格となる原価があってその差額が利益額となります。その利益によって、皆さんが給料をもらったり生活ができています。もちろんこの利益額が低く、それ以上に皆さんの給料や社会保険費用や福利厚生費を含め営業経費などがそれ以上にかかると借金をしない限り、途端に経営そのものをあきらめなければなりません。
これが基本的な社会のルールであり、住宅業界でも同じことが言える
のです。
つまり、家づくりというのは、皆さんが契約してご依頼する工事価格=原価+利益額となっています。例えば、同じ2000万の家でも、原価1600万+利益額400万(利益率25%)と原価1200万+利益額800万(利益率40%)の家が存在し、原価が違うという事は、おおよそ性能や品質・構造などが違うであろうという事が予想できます。

で、この原価の構成は、商材と職人の手間となり、商材とは、システムバスやキッチンに床、壁の下地材や構造材、屋根材や外壁材、基礎のコンクリートや配筋などがあり、一方、手間の費用とは、ご想像通りで大工や左官、内装や設備など様々な職人さんの手間賃となります。
時折、住宅会社のチラシなどで「大量仕入れでお安くご提供!」と大量に安い価格で仕入れて、さも消費者に還元しているように説明をする会社もありますが、本当にローコスト住宅を販売するのであれば、商材だけではなく、この手間賃も経費までも下げる必要がある!という理屈になりますが、では、この職人さんの手間賃が、職人不足と言われている時代に果たして簡単に下げることができるのでしょうか?そもそも下げて良い職人が携わってくれるのでしょうか?ある某住宅会社では、一般の新築市場価格の半値の手間賃で発注していると耳にしたことがありますが、そんな事をして、消費者が心から信頼を寄せる事ができる腕の良い大工さんに出会えるのでしょうか?
仮に本当にそうであるなら、なぜ半値の手間賃で納得して工事を請ける必要があるのでしょうか?という素朴な疑問も感じるかと思います。そう、これをお読みの消費者であるあなたが、仮に腕のいい大工として考えればわかるかと思いますが、本当に性能も品質も良くてローコストであるというのであれば〝理想〟と言えるのですが、これらが価格の理屈となっております。
ところが、ここで “本当に性能も品質も良くてローコストであれば・・・” と書いているように実際に商材も手間もどちらもコストカットすることをしても、そのローコストを強調している会社の販売方法が多額のコストをかけて販売していて、展示場や宣伝ツール、住宅を販売する営業マンなど販売のための経費などが必要とする会社が多く、一般の中小の工務店のような利益率では、そのような住宅会社の経営が継続できないことになっていくのです。
となれば、利益率や額を多くする必要があるので、どこかでその額や率を帳尻合わせ、つまり利益を得なければいけません。それが、彼らの売り方とは切っても切れないオプションや別途という項目につながっていくのです。
つまり仮に同じ原価であっても、利益率さえコントロールすれば、意図も簡単に売価はどのようにも調整ができるという事になるものなのです。
また逆に会社の経営状態によっては、例えば数件の契約があり、会社も担当者の目標数値としても余裕があるときには、比較的その利益率も低くても認められる場合もありますが、逆に目標の数値が未達成で会社全体の売上や粗利の額の数字にピリピリしている時期などは、通常より高い粗利額で契約になるように仕向けられるものであり、つまり、契約の時期や担当者によっていとも簡単に販売価格が変わるものでもあり、消費者に対して全く公平ではないのです。

このように消費者である建て主の方は、信頼された気持ちで家づくりを頼まれているのに、その契約時期や担当者によって、利益額も違い契約金額も変わってくるのが、営業担当者が窓口となる住宅会社の実態とも言えます。
過去に耳にしたある工務店などは、高い利益率で提示したものの契約率が落ちたので、途端に方針を変え、慌てて利益率より契約をする事に重きを置き、契約後に市場価格より相当高い価格で追加や別途の請求をして、裁判になるまでのトラブルが相次ぐ会社もあるようですが、これは、ハウスメーカーなどでもよくある話で、中身を曖昧にしてさほど詰めずに契約に重点をおく家づくりはこうなってしまいます。
これらについては、私たちプロが見ても、利益率をいくらに設定しているのかが全く見えませんし、それを公開して教えろ!と言っても、9割以上の会社は、秘密主義で教えることなどありません。
また同じように見える工務店でも、利益を10%台に設定している会社から(しかしながらこれから先の経営状態が心配)ハウスメーカー並みの35%以上の高い利益率を設定している工務店もあったりしますし、原価に関して、高級な仕様や仕入れが高いモノを選べば、原価は上がるのがあたりまえの理屈なので、その点も消費者もわからないと言わないでしっかり意識されることが大切です。
いずれにしても、同じようなプランと性能や仕様なのに原価が違ったり、利益額や率がわからないので、消費者には価格の差が理解できない、全く見えないのが今の家づくりと言えますから、このハウスネット1000〜家づくりパートナープロジェクトでは、これらの原価なども情報公開して、利益率もお伝えして消費者にとってわかりやすい、見える家づくりを目指しています。
結局は、原価+利益額という住宅価格は、建て主であり依頼主であり消費者でもあるあなたのご家族に対して、原価が安い家を高く売る会社はいくらでもありますが、原価が高い家を安くは売ることなどはご商売としてはしてはいけない事です。それらが住宅価格の理屈となっています。