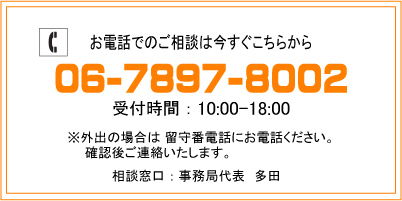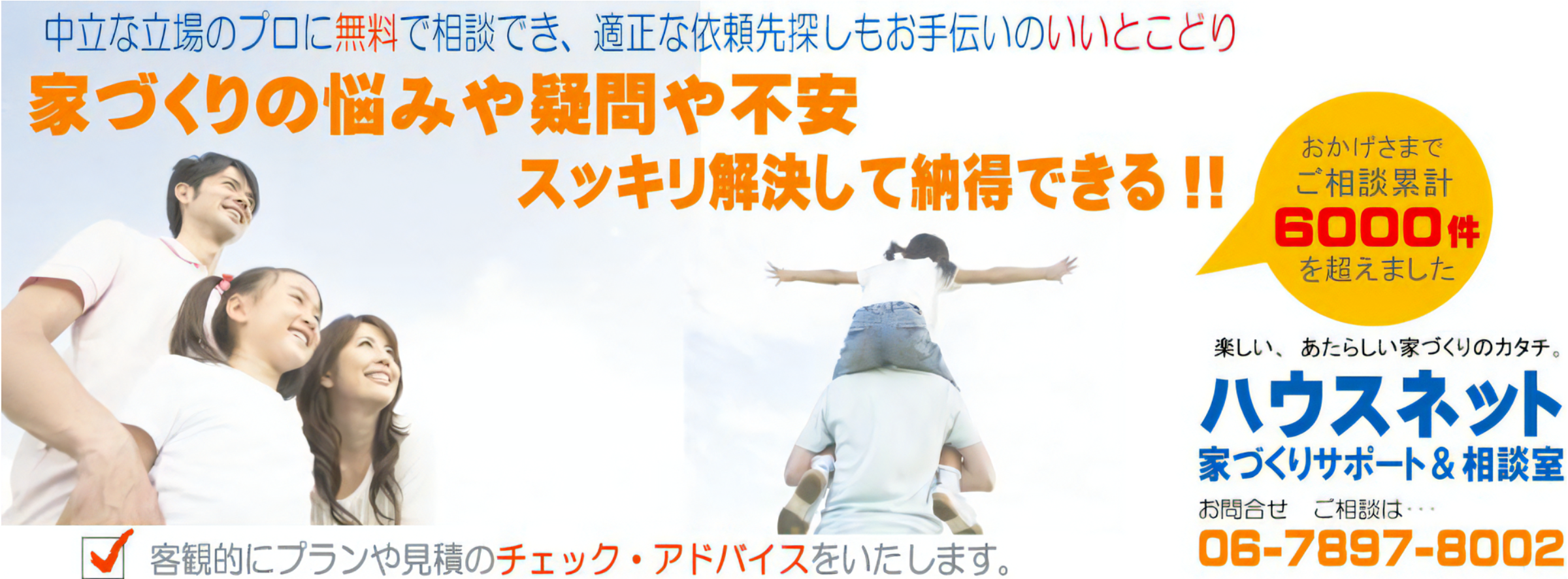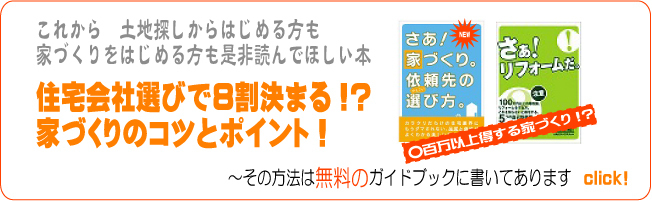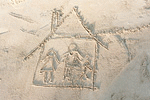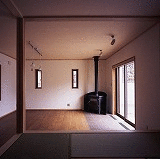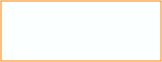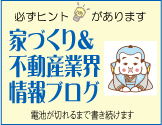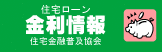これをお読みの方の中で経験者もおられるかと思いますが、親(義親含め)が亡くなった時の実家の片付けは、モノがあふれていて大変です。この経験をしたら皆さんもきっとわかるかと思いますが、自分がこの世からいなくなる前に残された身内に迷惑をかけないでおこうとモノを減らすことをはじめました。同時に本屋に行けばすぐにわかりますが、今〝ミニマリスト〟や〝モノを持たない暮らし〟などの関連本が流行っているようです。
だからというわけではありませんが、昔と違って家族数が少なく、この先の経済の不安からも若い世代に〝便利な場所〟での〝小さな家〟を望む人が増えると思われます。田舎で大きな家に暮らすよりも、小さくてもいいので便利で楽しく都会で暮らしたい!という考えになるのではないでしょうか?
捨てない主義でモノを持ちすぎて部屋に物があふれる昭和世代と違って、モノに対しての執着心もそれほどなく、買う時はいいものを買って長く持とうとして、カーシェアで車も持たない主義、フリーマーケットやネットのオークションで人に喜んでもらいながらも販売して気軽に手放して処分したり購入したり、自分のモノの総量を調整したりできる人が多い世代がこれから親になる時代であると思われます。
個室空間が外でも可能な時代に
一人暮らしのワンルームの生活が慣れたのか、小さい家だからリビングが小さくなっているわけでもなく、部屋にさほど大きさを持たないようで寝ることさえできたらいいあんばいの広さ程度でリビングに大きなテーブルを置いて、そこで子供は勉強したり、親が持ち帰ったちょっとした仕事をそこでおこなったり、ソファーで寛ぎながら気軽にスマホをしたりするスタイルで、どうやらプライバシーに対する意識が変わってきているのではないでしょうか?
スマホやネットのない時代である高度成長期から平成前半までは、個人主義でもあり親子間でもプライバシーを尊重しあうのはあたりまえで、電話、テレビ、音楽、ラジオ、インターネットなどはスマホに集約されて、外出して移動中でもカフェでもできるようになったので街中どこでも個室的な空間となり、部屋に閉じこもる必要はなくなってきていますので、そういう世代が親になると壁もつくらずにできるだけ広く空間を活用したいとなりつつあります。
また今の世代の人は、展覧会に数十万人並んで数時間待ちなど20年以上も前には考えられなかったのですが、日本の文化に対しても素晴らしいと思う感性もあるようで古民家をカフェにしたり住んだり、昔のデザインやアンティーク家具や古道具なども人気があり、ウサギ小屋と揶揄され欧米文化に多大なる影響を受けた日本の住宅を含め、もう一度日本の暮らし方を見つめなおそうという方向になっていっているかもしれません。
新しい日本らしいライフスタイルに突入!?
昔の日本の家には柔軟性がありました。ひとつの部屋が布団を敷けば寝室、ちゃぶ台を置けば食堂、ふすまを外せば2つの和室が大広間になったように部屋名を固定させずに道具の出し入れだけで自由自在に使い分けていたのです。

エコロジー意識も高くて、窓まわりでは、夏の陽射しを避けて冬の陽射しを取り込めるように庇を付け、窓外でよしずや簾を上手に活用し、格子を付けて目線は通さないけど風は通すように工夫されていたり、路上では打ち水したり、襖を閉めても欄間で風が抜けるようにされていました。
ところが海外から揶揄されて、ハウスメーカーができた頃から住宅業界全体やマスメディアや学者などまでも、モノを置いて部屋の機能を決める欧米とは、そもそもの国土の広さが違うのにその欧米式の寝食分離を提唱し始め、西洋の暮らしを真似るようになりましたが、大きな震災を経て、価値観に対しての考えも世代も変わりはじめ、ようやく西洋的なライフスタイルを勉強してまねる時期を終え、これからまた新しい日本らしいライフスタイルを確立していく時代に入ったようです。
リビングに大きなテーブルを置いて家族(家族のカタチも様々)で共有したり、リビングを和室として食事した後は、そこで布団を出して寝たり、天気のいい日は、ピザなど頼んでラフに庭で食事をしたりするかもしれません。
住まい手も参加する楽しい家づくりをする時代
今までの住まいに対する考え方などは、消費者がつくってきたものではなく、マスメディアを利用して住宅業界を引っ張ってきたハウスメーカーが推奨する家づくりを繰り返されてきました。学生や若い社会人の間は古い木造アパートからワンルームマンション、若い家族は団地から分譲マンションと変わり、マンションの間取りは全国的にどこも長谷工間取りでよく似ています。
それがここ最近では、大量生産的なコピーされた家ではなく〝自分らしい家に住みたい〟と考える人が多くなり、住まいへの向き方がそれがあたりまえになってきたとも言えます。自分なりにDIYなどが流行することもこれに関連する事かと思われます。

有名な9坪ハウスのように建築家のように作品づくりを追っかけない限り、売る側は商売的に小さな家を推奨しませんし、望まれていません。そんな売る側の立場の方々に言われるままにむやみやたらと床面積を増やして、モノを置く場所をたくさん作り、部屋の体積も増やして、環境負荷のかかる家づくりをこれからはやめてみましょう。
そのためには、理解ある設計者やそれを望む住まい手が協力して色々な工夫が必要であり、課題に対して知恵を絞って解決する楽しさにも気づき始めているかもしれません。
建築場所がいい中古を買って好きな間取りに変えたり、便利な場所で小さい家を建てて暮らす。
家も大きさではなく、センスの良いもの、いい素材・いい性能のものを最小限必要な分だけ持つそんなミニマムで持たない暮らしが新しくなっていくのではないだろうか?
次第に完成させる家づくりの考え方
住宅はお金さえかければ、どなたでも〝良いもの〟ができるというわけではありません。いたずらにお金をかけたからと言って満足度が急激に高まるわけでもありません。本当に必要とするならば、そこはしっかりとお金をかけるべきですが今すぐに必要でないものまでかける必要はないのです。
そのためにはまずは発注者で住まい手でもある皆さんの意識改革も必要といえますが、家を建てることを職としない限り、さほど経験することではなく、賃貸でない限りそう簡単に建て替えや住み替えができるわけでもありません。
だからこそ、できるだけお金をかけてやれることはやったほうがいい!と思っていませんか?家を建てるプロたちがそう言っているからそのほうがいいだろうと思いこんでいる人が多いものです。
そこで忘れてはいけないのが、つくり手は同時に売り手でもあるから彼らの立場から発する言葉を鵜呑みにして振り回されてはいけません。言われるまま受け入れるといくらでも予算は高くなっていきます。

家づくりというのは、いきなり無理をしてはだめです。家族の変化に合わせて変えていけばいいのです。家ができる時に今必要なものがそろっていたら良し!と考えるようにしましょう。
例えば、1階に和室を今すぐ作らずに、将来万が一の際に和室が増築できるように考えておくなど必要なものを必要な時に付け加えるとか、ゆとりができたらプラスしていこう!という気持ちぐらいでいいと思います。
子供室は、しばらくは物置にするので内装仕上げはしなくていいや!とか、扉も今は不要であるとか、収納の扉も今はカーテンでしておいて、やはり必要である!と感じたならあとでつけてもらえばいいのです。
外構工事を含め、家が完成するときにMAX100と考えないで10−20年かけて次第に家が完成していくという考えをしてその期間も楽しみましょう。そうすれば、きっと家づくりそのものや今の生活にもゆとりや余裕が出るでしょう。
最初からできるだけ完璧に!と思ってMAX100で完成させて生活してしまえば、この扉はほとんど使わないで開けっ放しのままなど〝これ使わない!〟とか、もっとこうしておけばよかった・・・とか使い勝手が悪いこともあるかもしれません。
しかしながら骨組みであるスケルトン部分のプランや基礎や構造は、それらの変化に対応できるものを選んでおかなければなりません。大は小を兼ねるで比較的簡単に間取りが変更できるようにとかインフィル部となる設備機器の交換もしやすいとかメンテナンスに関して配慮しておいたほうがいいという考えになるわけです。
家族構成は、年齢とともに必ず変化しますので、その変化にあわせて段階的に住まいも成長させていき、快適さを維持して、今は無理なく建てることで生活のゆとりを持ってほしいと思います。

住まいづくりというのは、最初はまさしく白いキャンバスからはじまり、家具が入り、人が入り、木も育ち、所々傷もでき、家族数にも変化があったりしながら色づいていくものです。住みながらでもリフォームなら工事が可能ですし、ちょっとした事ならDIYで自分たちですることも素敵です。
将来 必要になるかもしれないから・・・という事で本当に必要になるかどうかもわからない空間を今すぐに作る必要はないのです。それがもし水まわりであるならすぐ設置できるように配管だけをしてもらっておけばいいのです。
家づくりのサポートをはじめた最初の頃、親と同居しなければならいかもなので…といわれていたお客さまは、10年後にご訪問したら、部屋を作らなくてよかった。子供の部屋が空いたので万が一の時は、そちらに住んでもらうと言われていましたが、おそらく建築家やハウスメーカーや工務店にご相談していたら、その時積極的に部屋を造っていたでしょう。
少しでも、多くの利益や売上げ額の目標がある方々なのでそれは仕方がないことだとは思いますが、だからこそ住まい手となる皆さんの立場で、しっかり考えてアドバイスしてくれる相手を見つけて家づくりを進めるようにしてください
それが経済的にできる家づくりの最初の一歩かもしれません。